在留期間更新:技人国ビザの手続きと、企業の準備・注意点
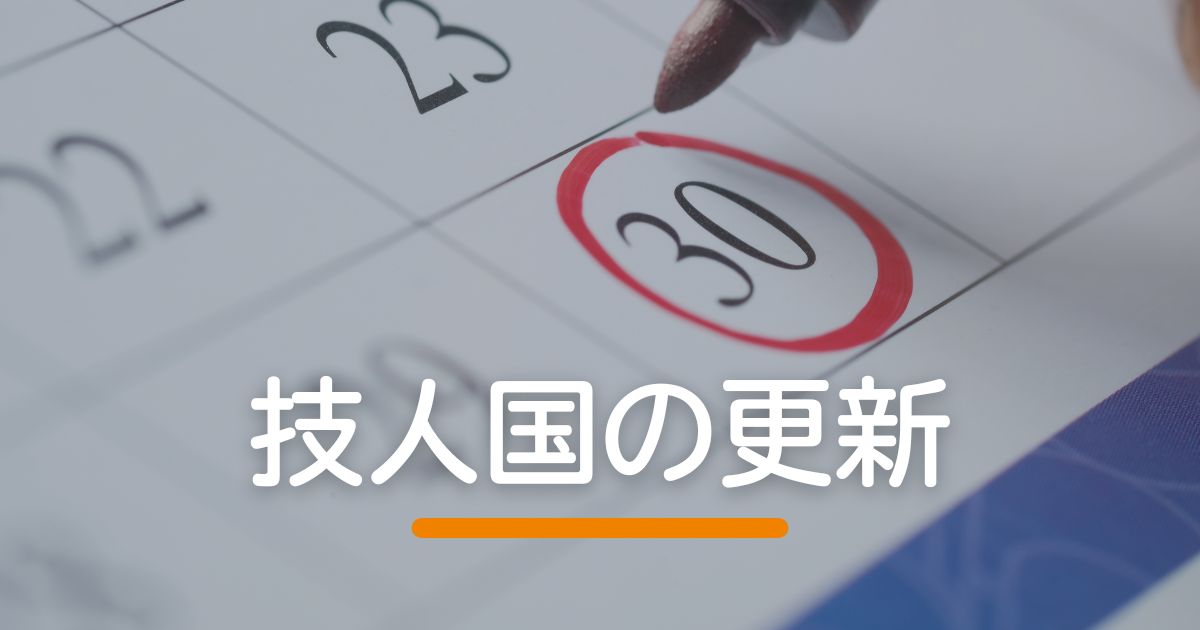
無事に外国籍社員の採用が成功しても、1年後または数年後には必ず「在留期間の更新」という手続きが必要になります。この更新手続きを失念したり、不許可になったりすれば、企業は貴重な人材を失うことになりかねません。
更新審査では、採用時とは少し異なる視点で、これまでの日本での在留状況が厳しくチェックされます。本記事では、企業の担当者が、社員の在留期間更新をスムーズに進めるために知っておくべき、審査のポイントと企業の役割について解説します。
更新審査で、入管は何をチェックしているのか?
在留期間の更新審査では、主に以下の点が確認されます。
- 活動の継続性: 引き続き「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な活動に、実体を伴って従事しているか。
- 報酬の妥当性: 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を、引き続き適正に受け取っているか。
- 素行の善良性: 日本の法律を遵守し、善良な住民として生活しているか。
- 公的義務の履行(納税・年金等): 住民税や年金・健康保険料などの公的義務を、期限通りに果たしているか。これは、在留資格の審査において、今後ますます厳しく見られることが確実な、非常に重要なポイントです。
【会社員の場合の注意点】 会社員の方の場合、所得税や社会保険料は給与から天引きされているため、この点で問題になることはほとんどありません。 しかし、転職時や扶養家族の状況変化など、ご自身で手続きが必要となるタイミングで、意図せず「未納」状態に陥ってしまうケースがあります。特に、入社1年目の住民税はご自身で納付する「普通徴収」の場合が多く、注意が必要です。
企業側が準備・確認すべき主な書類
更新手続きは原則として本人が行いますが、企業側で準備・発行が必要な書類があります。
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
-
会社の規模(カテゴリー)を証明し、給与支払いの実態を示すための、最も重要な書類の一つです。
- 住民税の課税証明書 及び 納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
-
これは従業員本人が市区町村役場で取得しますが、納税状況に問題がないか、企業側も内容を確認し、提出をサポートすることが望ましいです。
- 在職証明書
-
申請日時点で、確かに自社に在籍していることを証明するために発行します。
永住への道筋:在留期間「3年」が持つ特別な意味
更新時に許可される在留期間は「5年」「3年」「1年」「3月」のいずれかです。このとき、単に在留が「許可」されるだけでなく、「何年の期間が許可されたか」は、その外国人社員の日本での将来設計、特に「永住許可申請」において、極めて重要な意味を持ちます。
永住許可のガイドラインには、国益要件の一つとして「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」と定められています。「技術・人文知識・国際業務」の場合、法律上の最長の在留期間は「5年」です。
しかし、実際の審査運用を定めた出入国在留管理庁の内部基準である「審査要領」では、以下のように規定されています。
「当面、在留期間 「3年」 を有する場合は、 「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。」
つまり、永住許可を申請するためには、この運用に基づき、原則として「3年」または「5年」の在留期間を得ている必要があります。
企業として安定した雇用環境を提供し、社員が公的義務を果たせるようサポートすることが、結果として、その優秀な社員が「3年」以上の在留期間を得て、長く貴社で活躍してくれるための、最も有効なサポートとなります。
まとめ
在留期間の更新は、従業員本人だけの問題ではなく、企業の人事・労務管理の一環として捉えることが重要です。従業員の在留期限を社内で管理し、期限が近づいたら声をかけるといった配慮が、従業員との信頼関係を深め、安定した雇用に繋がります。 更新手続きにご不安があれば、ぜひ専門家である私たちにご相談ください。
「技術・人文知識・国際業務」の申請サポートについて
当事務所では、「技術・人文知識・国際業務」に関する各種申請を、専門家として強力にサポートいたします。






