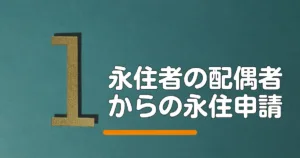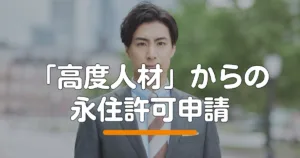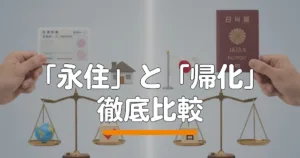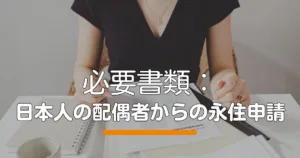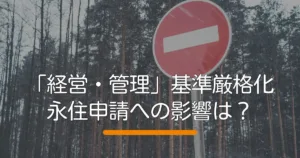永住申請と「税金・年金・健康保険」―国益適合要件としての公的義務履行
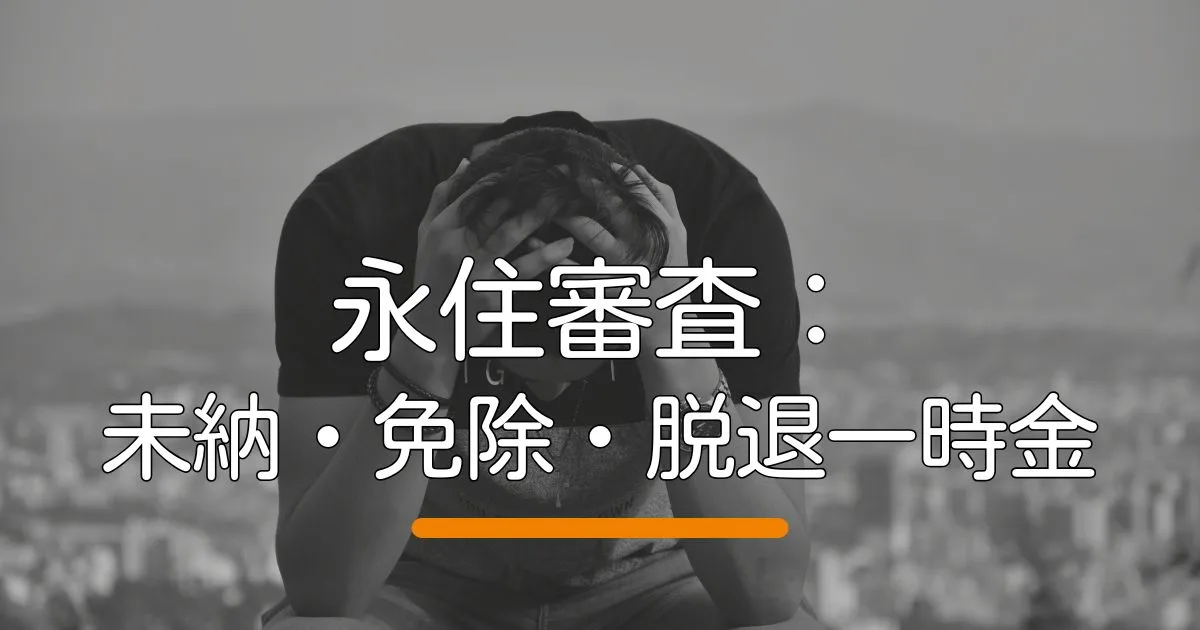
永住許可申請で最も厳しく審査される項目のひとつが、「公的義務の履行」――すなわち税金・国民年金・健康保険をきちんと果たしているかどうかです。
この公的義務の履行は、永住審査における 「国益適合要件」 の一部として評価されます。
「過去に少し払い忘れたことがある」「免除を受けていた期間がある」「家族が年金脱退一時金を受け取ってしまった」など、多くの方が不安を感じています。
このページでは、そうした過去の未納・免除・脱退一時金は大丈夫か?という疑問に答える形で、詳しく解説します。
永住許可全体の基本的な条件を確認したい方は、こちらの総合ガイドからご覧ください。

公的義務の履行(納税・年金・健康保険)
税金、年金、健康保険料の納付は、日本に住む住民としての基本的な義務です。これらの支払いに遅れや未納がある場合、「国益適合要件」に大きく影響します。
特に注意すべきは、審査で確認される期間です。
納税の義務
住民税などの税金を、定められた期限内にきちんと納付していることが求められます。永住審査では、原則として直近5年分が確認されます。
年金加入・納付の義務
国民年金または厚生年金に加入し、保険料を遅れずに納付していることが必要です。永住審査では、原則として直近2年分が確認されます。
健康保険加入・納付の義務
国民健康保険または会社の社会保険に加入し、保険料を納付していることが必要です。永住審査では、原則として直近2年分が確認されます。
この期間内に一度でも未納や遅延があると、その事実だけで不許可になる可能性が高いため、細心の注意が必要です。ただし、事情説明や完納により補正できる場合もあります。
口座引き落としまたは給与からの天引きでない場合、期限までに納付したことを証明する領収書等がないと、たとえ期限どおりに納付していたとしても不許可になる可能性があります。領収書等はなくさないよう細心の注意が必要です。
日本の公的年金制度の基本
まず、日本の年金制度の基本を理解することが重要です。日本の公的年金は、よく「2階建て」と表現されます。
- 1階部分:国民年金(基礎年金)
-
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する、基礎となる年金です。自営業者や学生(第1号被保険者)、会社員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)などが該当します。
- 2階部分:厚生年金
-
会社員や公務員が加入する年金です。厚生年金に加入する人(第2号被保険者)は、自動的に国民年金にも加入していることになり、保険料は給与から天引きされます。
原則として、この年金保険料を合計10年以上納付すると、将来、老齢年金を受け取る権利(受給資格)が発生します。そして、この受給資格期間(10年)を満した人は、後述する「脱退一時金」を請求できなくなります。
大原則:審査対象期間の「適正な納付」
まず、永住審査で重要になるのは、法律で定められた審査対象期間(原則として直近2年間の年金・健康保険、直近5年間の住民税)において、納付期限を守って適正に支払っているかどうかです。期限後に納付(納付遅れ)があっただけでも、審査に大きく影響します。
【重要】過去の「未納」や「免除」はこう見られる
多くの方が不安に感じる、過去の未納や免除が審査にどう影響するかを解説します。
税金や保険料の「未納」や「納付遅れ」があった場合
これは永住審査において最も致命的な問題の一つです。
特に、提出が義務付けられている審査対象期間(年金・健康保険は直近2年、住民税は直近5年)において、一度でも納付期限を守らなかった(遅れて納付した)という事実があれば、それは「公的義務を適正に履行していない」と判断され、不許可になる可能性が高いです。
また、審査対象期間より前の期間についても、審査官が必要と判断すれば調査される可能性があります。過去の納付状況は、申請者の遵法精神を判断する材料となるため、注意が必要です。
もし心当たりがある場合は、なぜ支払いが遅れたのか、現在はきちんと支払っていることを、理由書などで丁寧に説明する必要がありますが、非常に厳しい審査になることを覚悟しなければなりません。
国民年金の「免除」や「学生納付特例」を受けていた期間
「未納」と「免除」は全く違います。経済的な理由や、学生であったために、正規の手続きを踏んで国民年金保険料の支払いを免除、または猶予されていた場合、それは「未納」とは扱われません。
そのため、学生時代に「学生納付特例制度」を利用していた期間や、失業などで収入が減り「保険料免除・納付猶予制度」の承認を受けていた期間が直近2年間の審査対象期間に含まれていても、それ自体が直接不許可の理由になることはありません。
ただし、免除期間があまりにも長い場合、「日本で安定して生活できる資産や技能(独立生計要件)」という別の要件を満たしているか、という点で慎重に審査される可能性があります。
トピック①:年金の「脱退一時金」と永住申請
多くの外国人の方が、帰国する際に「年金脱退一時金」を受け取ることを検討します。しかし、この行動が将来にどう影響するか、正しく理解することが極めて重要です。
そもそも「脱退一時金」とは?
脱退一時金とは、年金の受給資格期間(10年)を満たさずに日本から出国する外国人の方が、それまで支払った保険料の一部を返還してもらえる制度です。これは、将来日本で老齢年金を受け取る権利を完全に放棄する(=これまでの年金加入期間がゼロになる)ことと引き換えに、一時金を受け取るものです
【シミュレーション】脱退一時金を受け取った場合 vs 受け取らなかった場合
Aさん(会社員)が、平均月収30万円で日本で5年間働き、厚生年金に加入。その後、一度母国へ帰国。数年後、再び来日し、同じく平均月収30万円で10年間働いた。
ケース1:帰国時に脱退一時金を受け取った場合
- 最初の5年分の厚生年金に対する脱退一時金として、約99万円を受け取ります。
- しかし、この時点で最初の5年間の年金加入記録は完全にリセットされます。
- 再来日後に10年間働いたため、最終的な年金加入期間は「10年」となります。
- 将来受け取れる老齢年金(年額)は、老齢基礎年金(10年分)と老齢厚生年金(10年分)を合わせて、約39万円になります。
ケース2:脱退一時金を受け取らなかった場合
- 帰国時に一時金は受け取りません。最初の5年間の年金加入記録はそのまま保存されます。
- 再来日後に10年間働いたため、最終的な年金加入期間は合計「15年」となります。
- 将来受け取れる老齢年金(年額)は、老齢基礎年金(15年分)と老齢厚生年金(15年分)を合わせて、約59万円になります。
結論
このケースでは、目先の約99万円を受け取ることで、将来の年金が毎年約20万円も少なくなってしまいます。わずか5年で、受け取った一時金の額を上回る損失が出ることになります。
脱退一時金の受給は「永住意思に反する行動」と見なされる
まず大前提として、脱退一時金制度は、将来日本で年金を受け取る資格を得ない(=日本での生活を終える)外国人のための制度です。 これを受け取るという行為は、入管に対して「少なくともその時点では、日本に永住する意思がなかった」という明確な意思表示と解釈される可能性が非常に高いです。これは、永住許可の根本的な要件である「永住を希望していること」と矛盾するため、永住審査においては極めて不利な事実として扱われます。
この前提を踏まえ、誰が一時金を受け取ったかによって、審査への影響度合いを見ていきましょう。
ケース1:申請者ご本人が脱退一時金を受け取っていた場合
まず、永住を申請するご本人が過去に脱退一時金を受け取っていた場合はどうなるのでしょうか?
◎「受給後〇年経てばOK」という明確な基準はない
まず、「受け取ってから5年経てば大丈夫?」「10年経てばリセットされる?」という疑問についてですが、そのような明確な年数基準は存在しません。在留期間のカウントは継続されますが、入管が問題視するのは経過年数ではなく、「一度は日本を出るつもりだった人が、なぜ考えを変えて永住したいと思うようになったのか?」という理由の合理性と、受給後の年金納付実績です。
◎ クリアすべきハードル
年金脱退一時金の受給歴がある方が永住申請に臨む場合、通常の申請以上に厳しい審査を覚悟し、以下の点を丁寧に立証していく必要があります。
- 理由書での詳細な説明(最重要): なぜ一時金を受け取ったのか(当時の状況や考え)、なぜその後永住したいと考えるようになったのか(具体的なきっかけ、生活状況の変化など)、その経緯を矛盾なく、客観的な事実(結婚、子の出生、就職など)と整合性をとりながら具体的に説明します。
- 年金への再加入と継続的な納付実績: 一時金受給後、速やかに公的年金に再加入し、申請時点まで一日も欠かさず保険料を納付していることを証明します(「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の記録など)。再加入後の納付期間が長ければ長いほど有利です。
- 他の要件の完璧なクリア: 居住歴、収入、税金・健康保険、素行など、他の永住要件に少しでも不安要素があると、一時金受給のマイナス要因と相まって、不許可のリスクがさらに高まります。
私は〇〇年〇月、以前の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の期間満了に伴い、当時は一度母国へ帰国し、日本での就労を終える予定でした。そのため、制度に基づき年金の脱退一時金を受給いたしました。
しかし、帰国後、[永住したいと考えが変わった具体的な理由やきっかけ。例:現在の配偶者と遠距離恋愛の末に結婚を決意した、日本の〇〇という文化に改めて魅力を感じ、日本で家族と生活基盤を築きたいと強く思うようになった、など] の理由から、再び日本で生活することを決意し、〇〇年〇月に再入国いたしました。
再入国後は速やかに年金制度に再加入し、現在まで継続して保険料を納付しております。過去に一時金を受給した事実はございますが、現在は日本社会の一員として安定した生活を送り、将来にわたって日本で暮らしていきたいという意思に、何ら変わりはございません。
(注: 上記はあくまで例文です。ご自身の状況に合わせて、正直に具体的に記述することが重要です。)
ケース2:配偶者が脱退一時金を受け取っていた場合
ご自身ではなく配偶者が脱退一時金を受け取っていた場合、それが「結婚前」だったのか「結婚後」だったのかによって審査への影響度が変わってきます。
- ケース1:結婚「後」に配偶者が受け取った場合(リスク:極めて高い)
-
これは、「永住申請を考えている世帯」そのものが、日本への定着性に反する行動を取ったと見なされます。申請者本人と生計を一つにしている配偶者が、日本での生活を清算するような行動を取ったわけですから、「この世帯は、本当に日本で永住する意思があるのか?」という、根本的な疑問を抱かせます。これは、挽回するのが非常に困難な、きわめて大きなマイナス評価となります。
- ケース2:結婚「前」に配偶者が受け取った場合(リスク:中程度)
-
申請者と出会う前の、配偶者個人の過去の判断です。しかし、永住審査は「世帯単位」で安定性や定着性を見るため、たとえ結婚前のことであっても、入管はその事実を把握します。この事実は、世帯全体の「将来にわたる日本への定着性」を評価する上で、一つの懸念材料として考慮されます。
結婚前に配偶者が受給していた場合の対策
この場合、一発で不許可になるような致命的な欠陥ではありませんが、何も説明しなければ審査官に不要な疑念を抱かせるリスクがあります。そのため、永住許可申請の「理由書」の中で、正直に、かつ積極的に事情を説明するのが最も良い方法です
「私の妻は、私と結婚する以前、技能実習生として在留しておりました。実習期間の満了に伴い、当時はそのまま母国へ帰国し、日本での生活を終える予定であったため、制度に従い年金の脱退一時金を受給しております。
その後、縁あって私と出会い、結婚し、現在は日本で安定した家庭を築いております。妻が過去に一時金を受け取った事実はございますが、それは私と出会う前のことであり、現在の私たちの世帯が、将来にわたって日本で生活していくという意思に、何ら変わりはございません。」
(注: 上記はあくまで例文です。ご自身の状況に合わせて、正直に具体的に記述することが重要です。)
【結論】脱退一時金を請求すべきかどうかの判断
このシミュレーションと永住審査への影響を踏まえると、判断基準は明確です。
- 絶対に請求すべきでないケース: ご自身または配偶者が、将来少しでも日本で永住申請をする可能性がある場合。目先の一時金のために、将来の永住への道を閉ざしてしまうリスクはあまりにも大きすぎます。
- 請求してよいケース: 将来、日本に長期的に関わる可能性(永住、再入国しての就労など)が全くないと断言できる場合。
トピック②:産休・育休期間中の社会保険
妊娠・出産は人生の大きなイベントですが、その期間中の社会保険料の扱いが永住審査にどう影響するか、心配される方は多いです。
休業期間中の社会保険料(年金・健康保険)は全額免除されます
産休・育休の期間中、会社を通じて年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を提出することで、ご本人と会社負担分の両方の社会保険料が全額免除されます。 これは「未納」とは全く異なり、正規の手続きによる「免除」です。そして、この免除期間も、将来の年金額を計算する上では、保険料を納付したものとして扱われます。 つまり、将来受け取る年金額が減ることはありません。
永住審査への影響:全く問題ありません
正規の手続きに基づいて社会保険料が免除されているため、産休・育休の取得が永住審査で不利になることは一切ありません。 重要なのは、会社が免除手続きをきちんと行っているかです。給与明細などで、休業期間中に保険料が天引きされていないかを確認するとよいでしょう
まとめ:公的義務の履行は、専門家による正確な確認が不可欠です
永住審査における税金や年金、健康保険の納付状況は、単に「払っているか」だけではなく、「いつ、どのように払ってきたか」まで厳しく見られます。過去のわずかな納付遅れ、正規の免除、そしてご自身やご家族の年金脱退一時金の受給歴など、一つひとつの事実が審査に大きく影響します。
当事務所では、お客様一人ひとりの複雑な納付・受給歴を精査し、永住許可の可能性を正確に診断します。少しでもご不安な点があれば、手遅れになる前に、お気軽にご相談ください。
「永住者」の申請サポートについて
当事務所では、「永住者」に関する各種申請を、専門家として強力にサポートいたします。
お客様の状況に合わせた3つの料金プランをご用意しております。